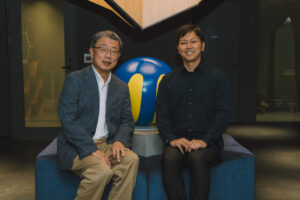2025.08.29
対談
LTVから始めるマーケティングの再設計 ──実務と学術の両面から探る、これからの広告のあり方とは【後編】
#マーケティング

MEMBER
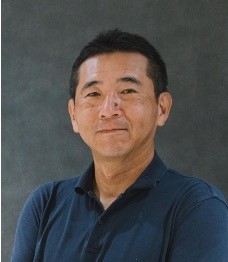
青山学院大学 経営学部
マーケティング学科 教授
小野 譲司さま
慶應義塾大学大学院で博士(経営学)を取得し、2011年より現職。CS・CXなど顧客満足の理論と実証を研究。関連著書多数。

株式会社Macbee Planet
代表取締役社長
千葉 知裕
公認会計士。大手監査法人を経てMacbee Planetに入社。2021年より代表としてグループ全体を統括。
運用型広告は、成果に直結しない──。そんな課題意識が、マーケティングの現場で広がりつつあります。マクビープラネットが全国1,063名のマーケティング担当者を対象に実施した調査では、4割以上が運用型広告に「満足していない」と回答。その背景には、CTRやROASへの不満、社内リソースの不足といった構造的な課題があるようです。
一方で、成果に応じて費用が発生する「成果報酬型広告」に対しては、大企業で60.5%、中小企業では71.2%が「満足している」と回答。無駄な広告費を抑えられる点が評価されたものの、未導入企業では「信頼できるパートナーがいない」「効果に不安がある」といった懸念があるようです。
そもそも広告における「成果」とは何を指すのか。そして成果報酬型広告は、企業のマーケティングに、どのような変化をもたらすのか。青山学院大学の小野譲司教授と、マクビープラネット代表の千葉知裕が、調査結果をふまえながら企業戦略の本質に迫る、本対談。
後編では、組織の課題にも踏み込みながら、マーケティング戦略における広告のあるべき姿を深掘りしていきます。
前編はこちら>>>
一方で、成果に応じて費用が発生する「成果報酬型広告」に対しては、大企業で60.5%、中小企業では71.2%が「満足している」と回答。無駄な広告費を抑えられる点が評価されたものの、未導入企業では「信頼できるパートナーがいない」「効果に不安がある」といった懸念があるようです。
そもそも広告における「成果」とは何を指すのか。そして成果報酬型広告は、企業のマーケティングに、どのような変化をもたらすのか。青山学院大学の小野譲司教授と、マクビープラネット代表の千葉知裕が、調査結果をふまえながら企業戦略の本質に迫る、本対談。
後編では、組織の課題にも踏み込みながら、マーケティング戦略における広告のあるべき姿を深掘りしていきます。
前編はこちら>>>
広告成果は“LTV視点”で再設計できるか?
━ 成果報酬型広告の課題を挙げるとしたら、どのようなものがありますか。
千葉:
やはりCPA(顧客獲得単価)やCVR(コンバージョン率)のような短期的な指標に偏りすぎて、その先のLTVまで見えていないことだと思います。
日本企業は、大企業になるとマーケティング組織がサイロ化していて、CPAやCVRで目標管理されているケースも多いため、現場の視野がどうしても狭くなってしまいがちです。そのような企業のご担当者様にLTVの重要性をお伝えしても、なかなか理解を得るのは難しいのが実情です。
さらに言えば、お客さま側で広告設計まで手が回らないケースも少なくありません。だからこそ、私たちがトータルソリューションとしてしっかり支援することが重要だと考えています。
具体的には、広告配信の条件設計や成果地点の定義といった初期設定の部分に加えて、どのデータを取得し、どう可視化し、どのようにレポートを設計するか、そしてコンバージョンの引き上げに向けた改善施策の提案まで含めると、支援の範囲は広範囲にわたります。
実際、そこまで踏み込めればいいのですが、中途半端な支援では成果に結びつけづらいのが悩ましいところではありますね。
日本企業は、大企業になるとマーケティング組織がサイロ化していて、CPAやCVRで目標管理されているケースも多いため、現場の視野がどうしても狭くなってしまいがちです。そのような企業のご担当者様にLTVの重要性をお伝えしても、なかなか理解を得るのは難しいのが実情です。
さらに言えば、お客さま側で広告設計まで手が回らないケースも少なくありません。だからこそ、私たちがトータルソリューションとしてしっかり支援することが重要だと考えています。
具体的には、広告配信の条件設計や成果地点の定義といった初期設定の部分に加えて、どのデータを取得し、どう可視化し、どのようにレポートを設計するか、そしてコンバージョンの引き上げに向けた改善施策の提案まで含めると、支援の範囲は広範囲にわたります。
実際、そこまで踏み込めればいいのですが、中途半端な支援では成果に結びつけづらいのが悩ましいところではありますね。
小野教授
(以下敬称略):
(以下敬称略):
マルチチャネルで複数の顧客接点を持っている企業はほんとうに多くなってきましたが、フィールド営業の活動履歴や店舗のPOSデータといったオフラインデータと、マーケティングが持っているオンラインデータが連携できていない企業は、まだまだたくさんありますからね。
データが統合されていないのも問題ですが、それ以前に、営業とマーケティングの間でLTVの考え方について合意形成されていないという問題もありますよね。
マーケティングとしては「LTVの高い顧客を育てるために、営業にはこんな活動をしてもらいたい」という要望があったとしても、営業は「反応の良いお客さま」や「話しやすいお客さま」のところにばかり足しげく通ってしまう、という現実もあるようです。
その結果、データ上は訪問数とLTVの間に相関関係があるように見えるのだけど、実際は、関係性の薄いお客さまのところへいくら頻繁に通っても、LTVが上がる、という期待される因果関係があるわけではない、ということです。
だからこそ、適切なデータを整備するとともに、マーケティングのデータや知見を活かして営業活動のロジックを組み立てたり、描いただけで次のステップに進めないで頓挫してしまうカスタマージャーニーマップを実運用に落とし込んだりするところが、御社のようなパートナー企業の腕の見せどころになるのではないでしょうか。
データが統合されていないのも問題ですが、それ以前に、営業とマーケティングの間でLTVの考え方について合意形成されていないという問題もありますよね。
マーケティングとしては「LTVの高い顧客を育てるために、営業にはこんな活動をしてもらいたい」という要望があったとしても、営業は「反応の良いお客さま」や「話しやすいお客さま」のところにばかり足しげく通ってしまう、という現実もあるようです。
その結果、データ上は訪問数とLTVの間に相関関係があるように見えるのだけど、実際は、関係性の薄いお客さまのところへいくら頻繁に通っても、LTVが上がる、という期待される因果関係があるわけではない、ということです。
だからこそ、適切なデータを整備するとともに、マーケティングのデータや知見を活かして営業活動のロジックを組み立てたり、描いただけで次のステップに進めないで頓挫してしまうカスタマージャーニーマップを実運用に落とし込んだりするところが、御社のようなパートナー企業の腕の見せどころになるのではないでしょうか。

“都合のいいLTV”が組織をミスリードする
━ マーケティング担当者が今後見直すべき「思考の枠組み」について、何かアドバイスがあれば教えてください。
小野:
過度に細かすぎるKPIに追われているマーケティング担当者の方には、何のためにそれをやっているのか、ぜひ一度立ち止まって、しっかりと考えることは重要ですね。
「ノルマだから」と思考停止しているのは、一番良くない。もちろん経営陣がLTVを理解したうえで中長期的な視点を持っていたら、そんなことにはなっていないでしょうけど。
千葉社長の印象としては、経営陣がLTVを理解して、ちゃんと指標設計までできている企業は、どれくらいあると思いますか?
「ノルマだから」と思考停止しているのは、一番良くない。もちろん経営陣がLTVを理解したうえで中長期的な視点を持っていたら、そんなことにはなっていないでしょうけど。
千葉社長の印象としては、経営陣がLTVを理解して、ちゃんと指標設計までできている企業は、どれくらいあると思いますか?
千葉:
経営陣のみなさんとしては、LTVを正確に把握したい気持ちは強く持たれています。けれども、現場から上がってくるレポートとの間に、実感とのズレを感じるケースが少なくないようです。
たとえば、業績が思わしくない局面でも、なぜかレポート上では数値が常に右肩上がりになっている。これは現場が恣意的に調整しているというよりも、評価制度との関係などから、どうしても“良く見せよう”という力学が働いてしまう構造的な問題だと思います。
結果として、LTVの算出ロジックも企業ごとにばらつきが出てしまい、共通の指標として使いにくくなる。これは現場を責める話ではなく、組織としての指標設計のあり方を見直す必要があるということだと感じています。
たとえば、業績が思わしくない局面でも、なぜかレポート上では数値が常に右肩上がりになっている。これは現場が恣意的に調整しているというよりも、評価制度との関係などから、どうしても“良く見せよう”という力学が働いてしまう構造的な問題だと思います。
結果として、LTVの算出ロジックも企業ごとにばらつきが出てしまい、共通の指標として使いにくくなる。これは現場を責める話ではなく、組織としての指標設計のあり方を見直す必要があるということだと感じています。
小野:
都合の良いLTVって、ありますよね。
大学院生にLTVの算出方法を教えるときに、購入単価・購入回数・継続期間をかけたものから、獲得コストや維持コストを引いて、割引現在価値も考慮して……と計算式を教えるのですが、「とはいっても、実際にこんな計算をしている会社のほうが少ないかもしれない」とも言っています。
コストは一切見ずに売上を顧客数で割ったものをLTVと言っていたり、LTVと言いながらも、実は単なるRFM(最終購入日・購入頻度・購入金額)しか見ていなかったり。企業によってLTVの算出方法が違うのは仕方がないにしても、その時々で都合良くLTVのロジックを変えるなんてことはやめたほうがいいと思いますね。
大学院生にLTVの算出方法を教えるときに、購入単価・購入回数・継続期間をかけたものから、獲得コストや維持コストを引いて、割引現在価値も考慮して……と計算式を教えるのですが、「とはいっても、実際にこんな計算をしている会社のほうが少ないかもしれない」とも言っています。
コストは一切見ずに売上を顧客数で割ったものをLTVと言っていたり、LTVと言いながらも、実は単なるRFM(最終購入日・購入頻度・購入金額)しか見ていなかったり。企業によってLTVの算出方法が違うのは仕方がないにしても、その時々で都合良くLTVのロジックを変えるなんてことはやめたほうがいいと思いますね。

信頼されるパートナーの条件とは
━ 小野教授は、マクビープラネットのようなパートナー企業が果たすべき役割は、どんなことだと思われますか?
小野:
第三者であるがゆえの存在意義みたいなものが、必ずあると思います。調査結果でも成果報酬型広告を「導入したことがない」理由として、大企業の約30%が「信頼できるパートナーが見つからない」という回答がありました。
事業会社のみなさんは他社の事例をものすごく気にされるので、「他社ではどうやってデータを可視化して、LTVのロジックを組み立てているのか」といった実践的な事例を示してあげると良いのではないでしょうか。
さらに言えば、信頼されるパートナーに求められるのは、単なる広告運用やレポート提供ではなく、企業内で分断されている「マーケティングと営業」「現場と経営陣」の間を橋渡ししながら、客観的な視点をもって各企業に最適なLTVを設定する力です。
そのためには、マーケティングやデータ分析に対する技術的な知見はもちろん、企業の組織構造や意思決定プロセスを理解したうえで、部門間の合意形成を促すファシリテーション力も不可欠になります。
現実と理想をつなぎ、戦略と実行を結びつける存在になれたら最高ですね。
事業会社のみなさんは他社の事例をものすごく気にされるので、「他社ではどうやってデータを可視化して、LTVのロジックを組み立てているのか」といった実践的な事例を示してあげると良いのではないでしょうか。
さらに言えば、信頼されるパートナーに求められるのは、単なる広告運用やレポート提供ではなく、企業内で分断されている「マーケティングと営業」「現場と経営陣」の間を橋渡ししながら、客観的な視点をもって各企業に最適なLTVを設定する力です。
そのためには、マーケティングやデータ分析に対する技術的な知見はもちろん、企業の組織構造や意思決定プロセスを理解したうえで、部門間の合意形成を促すファシリテーション力も不可欠になります。
現実と理想をつなぎ、戦略と実行を結びつける存在になれたら最高ですね。
━ では最後に、千葉社長に伺います。
今回の対談を通じての気づきや、今後マクビープラネットとして実現していきたいことを教えてください。
今回の対談を通じての気づきや、今後マクビープラネットとして実現していきたいことを教えてください。
千葉:
私たちは、企業のマーケティングパートナーとして支援している立場から、CPAやCVRといった短期的な指標だけにとらわれることなく、「獲得」を軸にしながらも、中長期的な視点で包括的にマーケティングの最適化を図ることを大切にしています。
そして、成果報酬型でLTVに基づいた成果を、しっかりと提供していく。お客さまの成果が上がれば上がるほど、私たちの収益も上がっていくというこのビジネス構造こそが、私たちの大きな強みであると考えています。
一方で、当社も上場企業である立場上、どうしても短期的な成果を求められる場面があるのも事実です。
そうした中で、小野教授のような第三者から客観的にご意見をいただける今日のような機会は、非常に貴重なものでした。今日の対話を通じて、マーケティングの本質を見失わないようにしなければならないと、改めて身が引き締まる思いがしました。ありがとうございました。
そして、成果報酬型でLTVに基づいた成果を、しっかりと提供していく。お客さまの成果が上がれば上がるほど、私たちの収益も上がっていくというこのビジネス構造こそが、私たちの大きな強みであると考えています。
一方で、当社も上場企業である立場上、どうしても短期的な成果を求められる場面があるのも事実です。
そうした中で、小野教授のような第三者から客観的にご意見をいただける今日のような機会は、非常に貴重なものでした。今日の対話を通じて、マーケティングの本質を見失わないようにしなければならないと、改めて身が引き締まる思いがしました。ありがとうございました。