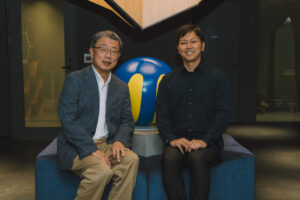2025.11.06
対談
広告の“目的”はどこにある? ──『認知』にとどまらない新しい広告のあり方を考える【後編】
#マーケティング
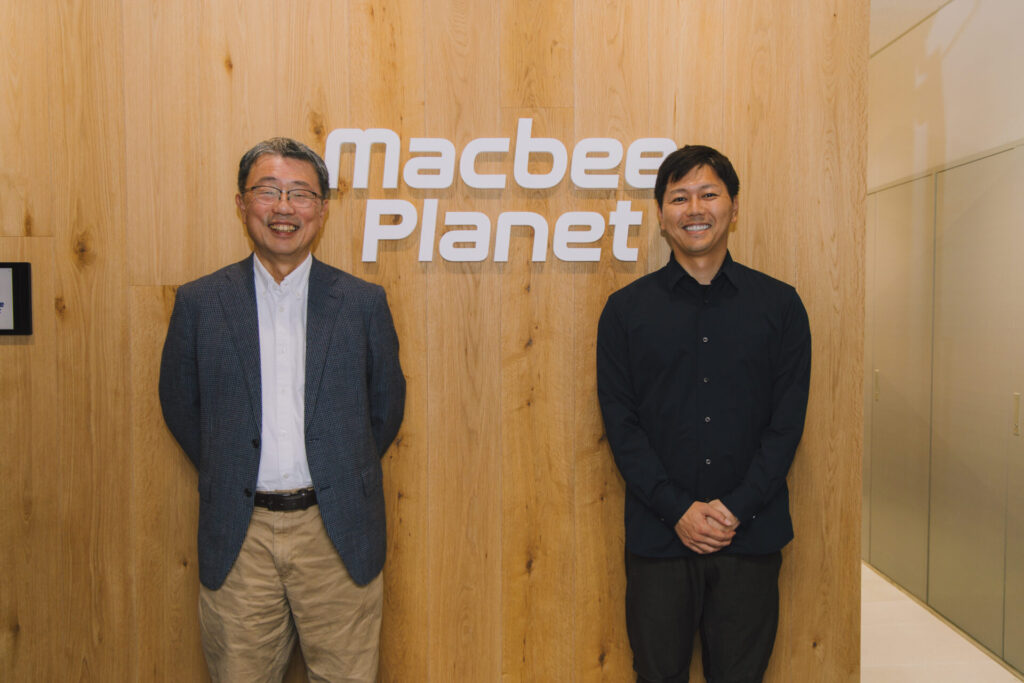
MEMBER
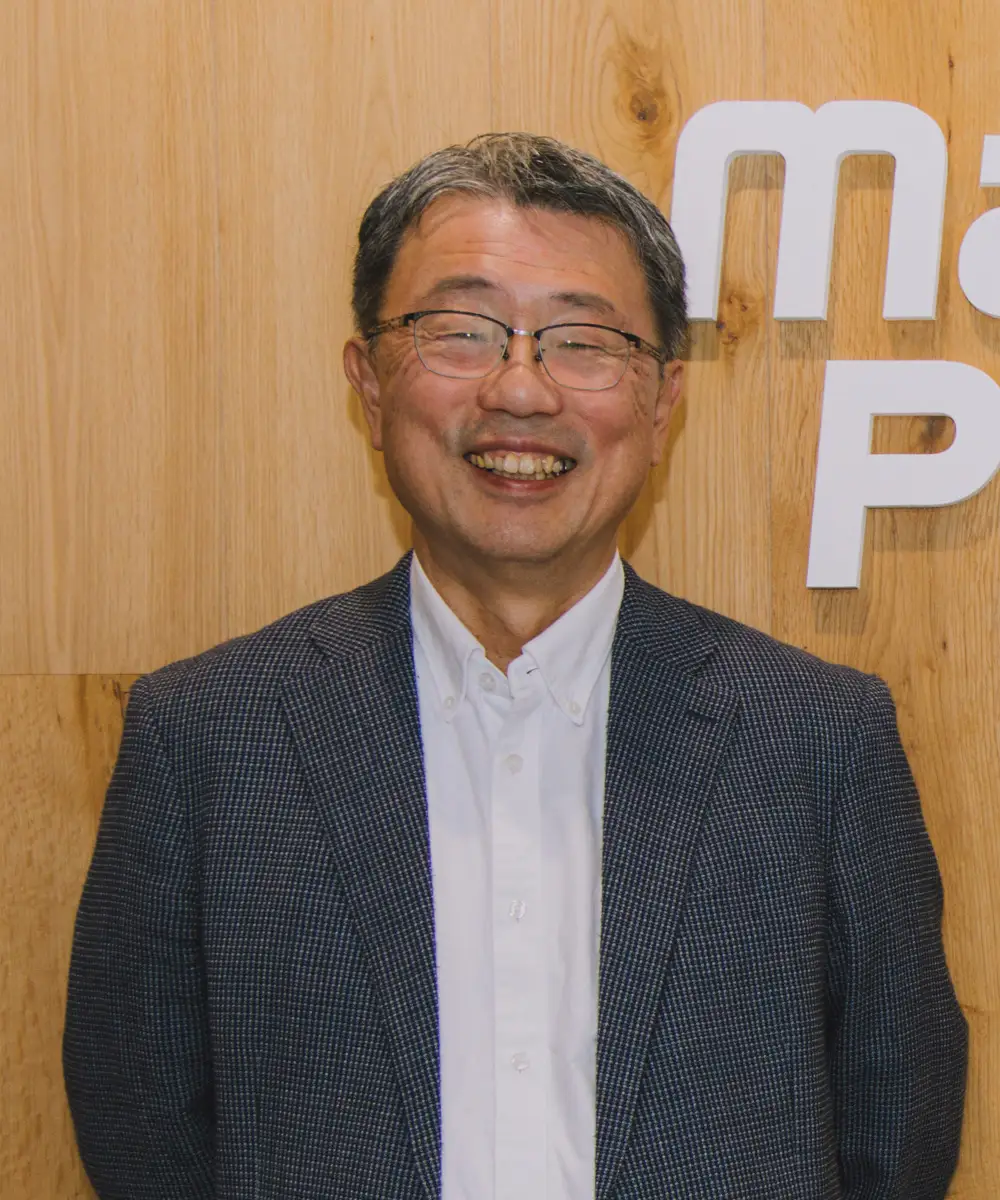
多摩美術大学 美術学部
リベラルアーツセンター 教授
佐藤 達郎さま
広告コミュニケーション論の第一人者。国内外の広告トレンドや創造性、社会との関係性を研究。

株式会社Macbee Planet
代表取締役社長
千葉 知裕
公認会計士。大手監査法人を経てMacbee Planetに入社。2021年より代表としてグループ全体を統括。
マクビープラネットが行った「広告の“目的と成果”に関する実態調査」では、約9割のマーケティング担当者が「認知広告は評価が難しい」と回答。“認知=成果”に疑問を抱く傾向が強まる一方で、広告出稿の目的は依然として「認知重視」が多数派を占めるという、構造的なギャップが浮き彫りとなりました。
このように広告の“目的”が形骸化すると、経営層と現場で認識の齟齬が生じ、投資配分の誤りやメッセージの分散など、マーケティング効果の低下を招きかねません。
広告の“目的”を認知だけに求める時代は、すでに終焉を迎えているのではないか——。この問いを起点に、多摩美術大学の佐藤 達郎教授と、マクビープラネット代表の千葉 知裕が、新しい広告設計のあり方を考察する、本対談。
後編では、広告の“目的”を成果へとつなぐ実践のヒントを、マクビープラネットの取り組みや最新事例を交えながら紐解きます。
前編はこちら>>>
このように広告の“目的”が形骸化すると、経営層と現場で認識の齟齬が生じ、投資配分の誤りやメッセージの分散など、マーケティング効果の低下を招きかねません。
広告の“目的”を認知だけに求める時代は、すでに終焉を迎えているのではないか——。この問いを起点に、多摩美術大学の佐藤 達郎教授と、マクビープラネット代表の千葉 知裕が、新しい広告設計のあり方を考察する、本対談。
後編では、広告の“目的”を成果へとつなぐ実践のヒントを、マクビープラネットの取り組みや最新事例を交えながら紐解きます。
前編はこちら>>>
“目的”から設計する広告とは何か?
—— 前編では、「広告の“目的”を問い直すべきだ」という議論がありました。では実際に、目的から広告を設計して、成果を上げた事例には、どのようなものがあるのでしょうか?
佐藤教授
(以下敬称略):
(以下敬称略):
代表的なもので言えば、ポカリスエットの「若者×ダンス」シリーズや、ゼスプリの「キウイブラザーズ」のCMが挙げられるでしょう。どちらも商品そのものを全面に打ち出すのではなく、社会の課題や価値観と自社の訴求ポイントをうまく結びつけているのが特徴です。
ポカリスエットは、近年、若者の表現や感情に寄り添うコミュニケーションに切り替えています。40年以上の歴史を持つロングセラー商品ですから、若者の間では「親世代が好む飲み物」というイメージが広がり、販売が伸び悩んでいたそうなんです。そこで、「10代・20代の若者に飲んでもらえるようにする」という目的を設定し、若者の共感性が高い「青春」「部活動」「ダンス」といったテーマを取り入れたキャンペーンを展開しています。
ゼスプリはキウイのブランドですが、「ヘルシーを、やみつきに。」をブランドメッセージに掲げ、健康的な生活を“努力”ではなく“楽しさ”から考えようという発想を訴求しています。CMでも「体に良いキウイを食べて健康になろう」とは直接的に語っていません。「日本人の3人に1人は『栄養不良』。完璧な食生活を続けるのは大変だから、楽しく手軽に栄養をとる方法を考えよう」と、社会的な課題から入り、“食生活の改善に取り組むブランド”としての信頼獲得を目指しています。
ポカリスエットは、近年、若者の表現や感情に寄り添うコミュニケーションに切り替えています。40年以上の歴史を持つロングセラー商品ですから、若者の間では「親世代が好む飲み物」というイメージが広がり、販売が伸び悩んでいたそうなんです。そこで、「10代・20代の若者に飲んでもらえるようにする」という目的を設定し、若者の共感性が高い「青春」「部活動」「ダンス」といったテーマを取り入れたキャンペーンを展開しています。
ゼスプリはキウイのブランドですが、「ヘルシーを、やみつきに。」をブランドメッセージに掲げ、健康的な生活を“努力”ではなく“楽しさ”から考えようという発想を訴求しています。CMでも「体に良いキウイを食べて健康になろう」とは直接的に語っていません。「日本人の3人に1人は『栄養不良』。完璧な食生活を続けるのは大変だから、楽しく手軽に栄養をとる方法を考えよう」と、社会的な課題から入り、“食生活の改善に取り組むブランド”としての信頼獲得を目指しています。
千葉:
商品・サービスが良いものであることは大前提として、その機能を直接訴求するのではなく、社会課題や生活者の関心を起点に広告の目的を考えることが重要なんですね。
佐藤:
そうです。ポカリスエットやゼスプリのような事例は、どちらも企業が伝えたいメッセージを、社会の関心ごとや生活者の実感と結びつけて表現している点が共通していますよね。このように、広告は社会の文脈の中で考えることが大切だと思っています。
つまり、「目的から広告を設計する」というのは、企業の伝えたいメッセージを、社会の中でどう意味づけるかを考えることだと言えます。こうしてできた広告には、単に商品の認知や購買を促すだけでなく、生活者との信頼関係を育む力が備わり、結果的にLTVの向上にも寄与していくのではないでしょうか。
つまり、「目的から広告を設計する」というのは、企業の伝えたいメッセージを、社会の中でどう意味づけるかを考えることだと言えます。こうしてできた広告には、単に商品の認知や購買を促すだけでなく、生活者との信頼関係を育む力が備わり、結果的にLTVの向上にも寄与していくのではないでしょうか。

目的ドリブンな広告設計の実現に向けて
——“目的”を明確に掲げた広告設計を阻む大きな壁は、何だと思いますか?
千葉:
大きな壁は、短期志向に陥りやすい日本の組織構造と雇用形態にあると思います。さらに言えば、日本の伝統的な採用の仕組みや、経営を取り巻く環境変化のスピード感なども関係していると感じます。
経営者の立場からして、この問題を解決するのは極めて難易度が高いと理解してはいるものの、獲得数や獲得単価のような直接的な数字に目が向きがちな現状を打破するには、こうした根本的なところから見直すしかないと思うのですが、いかがですか?
経営者の立場からして、この問題を解決するのは極めて難易度が高いと理解してはいるものの、獲得数や獲得単価のような直接的な数字に目が向きがちな現状を打破するには、こうした根本的なところから見直すしかないと思うのですが、いかがですか?
佐藤:
そうですね。以前から「日本にはCMOがいない」とか、「CMOとマーケティング本部長は機能が異なると理解していない」といった指摘があるように、長期的な視点で本質的なマーケティングを推進できる人材が極めて少ないのだと思います。その結果、現場の担当者に依存した、短期志向かつファネルが分断されたマーケティングに終始してしまう。
千葉:
まさに。そうなるとマーケティング支援会社としても、広告の正しいあり方や理想のコミュニケーションを追求できなくなり、本来の目的を見失いやすくなってしまう。結果として、クライアントの要望に応えること自体が目的化してしまうこともあります。
佐藤:
たしかに。“企業と社会の結節点”という広告本来の力を取り戻すためにも、企業の価値創造と結びつけた広告設計を、経営の一部として捉えることが重要だと思いますね。
単なる販促ツールではなく、企業が社会とどうつながりたいのかを示す“意思表示の場”としての広告を、目的ドリブンで設計する。こうした取り組みを実践していくうえで、御社のような企業が果たすべき役割は、非常に大きいのではないでしょうか。
単なる販促ツールではなく、企業が社会とどうつながりたいのかを示す“意思表示の場”としての広告を、目的ドリブンで設計する。こうした取り組みを実践していくうえで、御社のような企業が果たすべき役割は、非常に大きいのではないでしょうか。

LTVマーケティングで広告の力を取り戻したい
——今回の対談を通じての気づきや、今後マクビープラネットとして実現していきたいことを教えてください。
千葉:
千葉:今回、改めて感じたのは、広告やマーケティング施策を個別に見るのではなく、認知から獲得、そしてCRMまでを一連の流れとして設計することの重要性です。どこかひとつに偏るのではなく、それぞれの要素をバランスよく連動させながら、生活者との関係を深めていくことが大切だと思います。
そのためには、企業の経営レベルの目的から逆算し、マーケティングファネルを段階ごとに分解して考えることが欠かせません。各施策がどこに・どのように貢献するのかを明確にし、目的達成に向けたKPIを設定しながら、全体を設計していく。このような視点を持って、これからもお客さまのLTVマーケティングをご支援していけたらと考えています。
その先に、広告が敬遠されない時代を取り戻したいですね。かつて広告が文化をつくり、人々の心を動かしていたように、社会にポジティブな影響を与える存在として、再び受け入れられる未来になってほしい。そんな変化を少しでも後押しできるよう、私たちも挑戦し続けたいと思います。
そのためには、企業の経営レベルの目的から逆算し、マーケティングファネルを段階ごとに分解して考えることが欠かせません。各施策がどこに・どのように貢献するのかを明確にし、目的達成に向けたKPIを設定しながら、全体を設計していく。このような視点を持って、これからもお客さまのLTVマーケティングをご支援していけたらと考えています。
その先に、広告が敬遠されない時代を取り戻したいですね。かつて広告が文化をつくり、人々の心を動かしていたように、社会にポジティブな影響を与える存在として、再び受け入れられる未来になってほしい。そんな変化を少しでも後押しできるよう、私たちも挑戦し続けたいと思います。
佐藤:
すばらしいですね。昔の広告は、今以上に強制的に見せられるものだったからこそ、「せめておもしろいものにして、人々を楽しませよう」という意識が、クリエイターの共通認識としてありました。
今の時代も、チャネルが多様化したとはいえ、広告が社会の中で果たすべき役割は変わっていません。人々や社会にとって価値のあるメッセージを、どう設計し、どう届けていくか。千葉社長のような視点を持って真摯に向き合い続けていくことが、これからの広告に求められているのではないでしょうか。
今の時代も、チャネルが多様化したとはいえ、広告が社会の中で果たすべき役割は変わっていません。人々や社会にとって価値のあるメッセージを、どう設計し、どう届けていくか。千葉社長のような視点を持って真摯に向き合い続けていくことが、これからの広告に求められているのではないでしょうか。